昭和生まれの私、令和の時代に移行してふたつの山と谷を超えたような世代かと思います。
そうだ彼女のことを回想しよう。
山猿のような母方祖母、明治生まれでいつも桃割れを結って着物が似合う人だった。
彼女がはじめて大きな病いに倒れたのは、私が看護学生の頃。
病名は「くも膜下出血」で自宅玄関で発見され、同居していた伯父が吐瀉物を取り除き、救急処置を行った。
おそらく発見が少しでも遅れていると窒息によって、そのまま冷たくなってしまっただろうと思う。
救急搬送後、祖母は緊急手術を受け、似合っていた桃割れのヘアスタイルを断念した。
退院後は伯父家族が在宅介護を一気に引き受けていた。そして祖母は2階にあった自室を離れ、1階にある仏間に布団を敷き過ごすことになった。
当時は介護保険のかけらもなく、伯父は会社勤めをしながら夜間の付き添いを毎日引き受ける生活を送っていた。
私は、休みの日を利用して祖母の夜間の付き添いをかってでたが、たった一晩でギブアップしてしまう状況だった。看護学生というのは名ばかりで、全くもって情けない有様だった。
この時、在宅介護の大変さを痛感し、伯父家族には「ごめんなさい、ありがとう」と言うしかなかった。
それからしばらく祖母は伯父宅と伯母宅と老人病院を行ったり来たりしながら過ごすことになった。
みんな疲れていた。本当に疲れていた。
老人病院へ見舞いに行った時は、10名程度の入院患者が同じ室内で過ごしていた。
男性か女性かわからない様相で、誰も話しをする人はいなかった。
小さくなった祖母、何も言葉にすることができない様子で、たくましい山猿は生まれたての子猿のようになっていた。
ここでも私は、長く時間を過ごすことはできず足早に自宅へ戻ってしまった。
私たち親族全員は、1日でも長く生きていてほしいと思うと同時に、この介護生活から解放される日はいつ来るのだろうか、と考えずにはいられなかったと思う。
私は保健師として就職し、はじめてのゴールデンウィークを迎えていた。
寝静まった深夜、電話が突然鳴り響いた。
亡くなったという・・・まさか伯父が・・・
彼は大きな企業の中間管理職だったと記憶している。
気さくで明るい性格の伯父は、今まで病気らしい病気にかかったことがない人だった。
突然、心臓が停止したという。診断名は「心不全」だった。
私は購入したばかりの軽自動車に両親を乗せ、病院へ駆けつけた。
「嘘だろう・・・」
あまりにも突然のことで誰も事実をすぐには受け止められなかった。
そして私はまるで自分のせいで伯父を死なせてしまったような感覚に陥った。
伯父の通夜と告別式を終え、再び連絡が入った。
祖母が老人病院で亡くなったという知らせだった。
伯母が数日前に面会に行った時、不思議なことに祖母は自ら伯父の名前を発し
「〇〇、亡くなったな」と語ったという。
祖母は「おばあちゃん」になる前からずっと「おかあさん」だった。
息子の死をどうして知ったのだろう。
母として最も悲しい最期を祖母はむかえることになった。
私たちはゴールデンウィークに2回、火葬場に出向くことになった。
私はそれ以降、母方祖母と伯父の姿をあらゆる人々に転移させながら過ごすことになった。
夫と出会った頃、義母は「くも膜下出血」で寝たきりの状態だった。
私は何かに取り憑かれ、引き込まれ、やり直しを命じられたような感覚で結婚式を挙げることになった。
本当にこれで良かったのか?
それでも、この出会いがなければ私が私らしく生きる方向性を見失うところだったと思える。










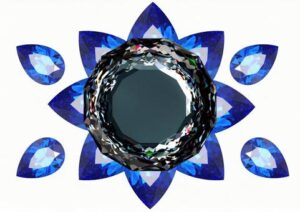
コメント